作文が苦手だった
わたしは作文が苦手な子どもでした。
読書感想文をはじめとした、作文の宿題や授業がとてつもなく嫌でした。原稿用紙1枚400字を埋めるにも、毎回「書けないー」と泣きながら宿題に向き合っていた記憶があります。体育の次に嫌いな科目でした。
そんなわたしですが、出来不出来はともかくとして、いまやブログ更新という形で文章を日々発信しています。作文に苦手意識を持っていたことが嘘のようです。
どこかで人格改造でも受けたのでしょうか。もちろんそんなことはなく、転換期となったのは、高校の頃だったように思います。
小学生の頃
小学生の頃。初めて原稿用紙に文章を書く「作文」という行為をしました。はじめは当然に未知の作業であったので、特別苦手意識を抱くには至りませんでした。
この頃の作文の授業といえば、当時の担任の先生に教えて頂いたことを今も律義に守っています。3点リーダーは偶数個で使用するということや、エクスクラメーションマークやクエスチョンマークは重ねず単独で使用するということや、数字の表記は縦書きならば漢数字、横書きならばアラビア数字にするということ……。何となく、ルーツのひとつがここにある気がします。
しかし、学年が進むにつれ、400字を埋めることに難しさを感じ、苦手意識を持つようになります。
泣きながら宿題をしていたのはこの頃ですね。母から「もし将来大学に行くことがあったら、卒業する為には長い作文(たぶん卒論のこと)を書かないといけないんだよ」と言われ、「じゃあそんなところ行かない!」と返した記憶がありますね。
中学生の頃
中学に入ると、流石に泣きながら書くということは無くなりましたが、やはり薄く敬遠していました。文章に親しむことが無かったわけではないのです。小学校中学校に通う間、学級図書や図書室、市の図書館の本を読む機会も多かったです。しかし、読むのが好きということとが、書くのが得意ということには繋がりません。
文章で自説を述べることが求められる機会も増えた頃、何故か急にどうにかできるようになりました。当時のわたしは、現在に連なる中二病の発症初期にありまして、持ち物に「意味」を持たせていました。数学には「計算が得意になる」このシャーペン、理科と社会には「暗記した言葉が引き出しやすくなる」このシャーペン……と、場面にあわせて筆記用具の使い分けをしていました。この道具を使えば、これを解決できるという自己暗示ですね。
そういった中で「作文能力を引き出す」黄色いシャーペンを使うことで、原稿用紙をスラスラと埋めることが出来るようになりました。もともと持っていた能力が暗示により使用可能になったのか、それとも、嫌々ながら真面目に宿題に取り組んでいたことの積み重ねにより書けるようになったのかは、わかりません。
高校生の頃
そして、転換期となる高校時代です。
友人を失う等々、人間関係の変化の大きかった時期ですが、一方でその他の環境にも変化がありました。祖母から、母・弟・わたし兼用で使うようにと、パソコンを買い与えられたのです。我が家にインターネットが導入され、文明開化がもたらされました。
インターネットが利用できるようになったことはもちろん、大きな変化なのですが、こと作文に関することでいうと、ワープロソフトが使えるようになったことが大きいです。
手先があまり器用でないわたしは、文字を書くのが遅く、頭に浮かんだ文章が文字にする前に消えてしまうということもありました。また、筆圧も弱く字が薄いので、文章の良し悪し以前に「読めない」と評されることも多かったです。
そこにワープロソフトです。書くよりも格段に速く、活字で文章が残せます。素晴らしい文明の利器です。
とはいっても、これが導入されてすぐに何かを書き始めたわけではありません。
人間関係の変化、機器の導入に加えて、読書傾向の変化もありました。この当時はライトノベルを読む機会が増え、後にギャルゲに手を出すことになります。
そして、思春期の全能感からか、「ラノベ作家になって、自作がアニメ化した折には好きな声優さんに主役を演じてもらう」などという「将来の夢」を持つようになりました。これに前後して、ようやくワープロソフトを活用し始めます。
主に人間関係の所為でつまらない学校生活により蓄積する一方だった鬱屈とした気持ちを、文章を書くという行為で多少晴らしつつ、自己投影と既存作品との継ぎ接ぎで、ライトノベル調のものをひとつ書きました。当時のテキストファイルは行方不明ですが、今読み返すと間違いなく悶絶するようなものなので、そのままでよいと思っています。
書き終えて気づいたことは、「目の前の光景ひとつをすべて文字で表現することもできずに、小説など書きようもない」ということでした。自分が想像している情景を読み手に伝えられないのでは、仕方ありません。
そう思いつつ書いた次の作品は、どういう経緯だったか、図書委員の後輩の女の子に読んでもらいました。肯定的な感想を得られましたが、今となっては本音かお世辞かはわかりません。
その後~現在の間のこと
その後、大学時代にはポメラを買ったことで作業が捗るようになりました。絵も曲も文も自分で作ったノベルゲームを1作完成させたり、書いた小説を印刷して簡易製本したものを「友人」に読んでもらったりしました。
その「友人」たちと共同してギャルゲを作るということに取り組んでいましたが、わたしの終身不名誉ストーカー関係のもめ事で人間関係が維持できなくなり、これは頓挫しました。これがあったので、何かしらの作品を誰かと合同で作るということに腰が引けてしまいます。いえまあ、その後に原作・わたし、画・妻で作った漫画があるので、まったくダメということではないのですが。
それはそれとして、気持ちが病むほど筆は乗るもので、先述の通り、小学生の頃に母から言われていた「卒業に必要な作文」もスラスラと書けました。自身がストーカーという悪性であると強く自覚させられたこともあり、「悪とは何か」というようなテーマで書いた気がします。
卒業後も作文は日常的に行っていました。業務日報であったり、社内での報告書であったり、役所に届け出る書面であったり、目的によって必要な内容を適した文体で書く日々でした。
その後は何のかんのとあって、このブログを開設するに至ります。作文に対する苦手意識は、今はありません。
おわりに
高校~大学当時は、書いた作品をインターネットに投稿するという発想はなかったですし、これまでに何度か作業環境が変化していてデータを移行していないので、現存している作品はほとんどありません。古いUSBなどを探せば見つかるかもしれませんが。
過去に書いたものが読み返せなくても、続きを書けず「第1話」で終わってしまった作品や、共同制作がとん挫したギャルゲも、それらを書いたことで「作文は怖くない」という意識が固定化できたので、無駄ではなかったのだと思います。
明確にいつのどれがというのは思い出せませんが、なにかしらで「自分にも書けた」と思える成功体験が、モチベーションアップにつながったものと思います。
かつての苦手意識はどこへやら。今となっては、書きたいものがたくさんあるのに時間と指先の巧緻性が追い付かないと、悩むようになっています。
人間、変われば変わるものですね。
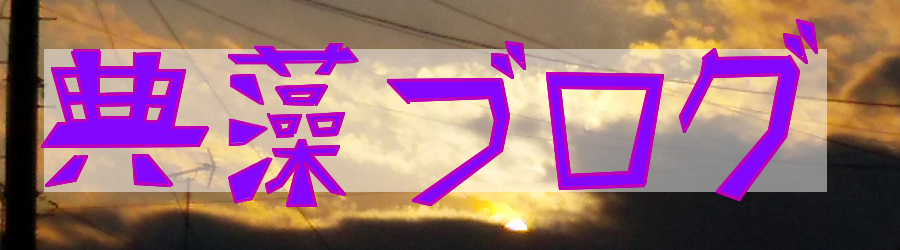


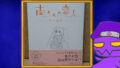
コメント